12月に赤玉土のみと籾殻のみで挿し木を行ったセルトレイ挿しの結果についてまとめていきます。
簡単に振り返ると、

このような形でそれぞれの挿し木を行いました。

今回は赤玉土と籾殻を使って、イチジクの挿し木にとってどのような効果や影響があるのかを探っていきます。果たしてどんな結果になるのでしょうか?
結果:発芽・発根はしたものの…?
約70日後にはこんな感じになりました。


かなり枯れてる…?

悲しみ…
発芽・展葉をした後に枯れていってしまったので、全部取り出してチェックしてみました。

発芽:25/25(100%)
発根:25/25(100%)
展葉:24/25(96%)
落葉:13/25(52%)
枯死:5/25(20%)
平均葉数:1.33枚(生存株の合計葉数:8、生存株数:6)

発芽:25/25(100%)
発根:24/25(96%)
展葉:23/25(92%)
落葉:5/25(20%)
枯死:4/25(16%)
平均葉数:2.57枚(生存株の合計葉数:36、生存株数:14)

別々に見てみると結構違うね
これを並べて比較すると次のようになります。


| 赤玉土 | 籾殻 | |
| 発芽 | 25 | 25 |
| 発根 | 25 | 24 |
| 展葉 | 24 | 23 |
| 落葉 | 13 | 5 |
| 枯死 | 5 | 4 |
| 葉数 | 1.33 | 2.57 |
発芽:50/50(100%)
発根:49/50(98%)
展葉:47/50(94%)
落葉:18/50(36%)
枯死:9/50(18%)
全体で考えると、発芽・発根・展葉の確率が90%を超えていますので、『Excel』は挿し木の初期段階としては成功率が高いのではないかと思います。
また、一覧表を見ると発芽・発根・展葉・枯死の4項目については最大でも1株の違いだけなので誤差の範囲だと思いますが、落葉数の差には大きな違いがあるます。
また、落葉していない株の葉数を比較してみると、赤玉土では最大葉数は2、籾殻では最大葉数は4となっています。平均の葉数では1.33と2.57と2倍近くの数値に開きが出ています。

全体的には赤玉土の方がいい感じだね
このことから、今回の挿し木では籾殻の方が成績が良かったことになります。今回の挿し木について次から考察していきます。
結果①:有機用土と無機用土の違い〜虫害について〜
計測しているわけではないのと、セルトレイの場所によって蒸発量などの変わるので誤差がある前提ではありますが、なるべく差が出ないように灌水のタイミングや量には気をつけたつもりです。
それを踏まえると、今回の結果は用土の違いによって発生したものと考えられると思いますので、それぞれの差に注目してきましょう。
まずは穂木の断面の状態についてです。

髄と呼ばれる枝の中心部分にある白い綿のような部分に大きな差がありました。

籾殻の方は空洞になってるね

籾殻の穂木に注目して見てみましょう


ボコボコになってる?もしかして…虫食い?
この写真を撮る前にはこの髄の部分には何匹かの小さいイモ虫みたいなものがいました。
おそらくはキノコバエの幼虫であると考えられます。観葉植物の土などに卵を産みつけて増える虫なので、有機用土である籾殻はキノコバエにとっては繁殖に適した場所だったのかもしれません。籾殻で育てた他の株もほとんどが食害を受けていました。
その一方で、赤玉土ではその被害は全く無かったので、無機用土であれば虫害を抑えられるのかもしれません。

赤玉土なら被害を受けなくなるかはもう一度実験してみないとわかりませんが、籾殻の方に被害を惹きつけるという結果が分かりました
結果②:食害と生育の差について
食害の有無が用土によって差があったことに伴って、食害を受けた籾殻挿し木の方が成績が悪くなりそうですが、無事な赤玉土の方が微妙な結果になりました。

なんか変だね…?

食害よりも悪い影響が別にあるのかもしれませんね
それを裏付けるのが、こちらの画像です。


カビてる…

どうやら深く埋めすぎて、上手く赤玉土を押し上げられずにカビてしまったようです
今回の挿し木では、セルトレイの真ん中あたりに穂木を置いたので、中粒の赤玉土では重すぎて押し除けられなかったことと、セルトレイの底の部分では赤玉土が砕けて泥のようになっていたのが影響している可能性が高いです。

赤玉土が小粒だったら、重さと強度が変わるので少し話は変わったのかもしれません
籾殻の方は軽いので展葉にとって負荷になりにくいことと、馴染んで保水性が上がったとしても、潰れて泥のような密度にはならないので、赤玉土よりは環境の悪化が進んでいないことが感じられました。
今回はどちらが良いかまではわかりませんでしたが、イチジクは浅植えの方が良いことは肝に銘じようと思います。

虫を飼うのは嫌なので、無機用土&浅植えで次はやります!
部屋にキノコバエが結構飛んでて不愉快だったので、色々な殺虫剤を探しましたが、これがかなり良かったです。

似たスプレーでも全部がキノコバエに効くわけじゃないので注意してね

効かないスプレーをし続けた過去が…
適用害虫にキノコバエがいるかが重要です。家用のスプレーにはユスリカやチョウバエ・ショウジョウバエに効くのが多いですが、これでは効きませんでしたのでメモとして残しておきます。

薬剤で誘引するのも効かなかった…

ハエの仲間ならなんでもいいわけじゃないんだね
脱線しましたが、最終的には単一用土の場合は、その用土が持つ特性を良くも悪くも最大限発揮してしまうことがわかりました。今回は赤玉土の使い方が悪かったというまとめになります。
結果③:挿し木成功に必要な穂木の重さは?
用土についての考察が終わったところで、次は挿し木の成功率と挿し穂の重さについてまとめていきます。
重さ別の成長状況について確認していきます。
| 2.0~2.9g | 3.0~3.9g | 4.0~4.9g | 5.0~5.9g | 6.0~6.9g | 7.0~7.9g | 8.0~8.9g | |
| 株数 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 |
| 発芽 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 |
| 発根 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 |
| 展葉 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| 落葉 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 枯死 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無事 | 2 (22%) | 1 (11%) | 3 (38%) | 4 (44%) | 5 (83%) | 3 (50%) | 2 (67%) |
最小の2.1gでは落葉はしてしまいましたが、展葉と発根までは成功しているので2.1gの小ささでも、挿し木は不可能ではないことがわかりました。

イチジクの生命力は凄まじいですね!
枯れているものは失敗確定ですが、落葉しているものは枯れているわけではないのでもう少ししたら復活するかもしれませんので、失敗とは言いにくいのですが、枯死も落葉もせずに乗り切った株の割合を見てみると、6.0g以上の挿し穂だと成功率が50%を超えることになりました。

5.0〜5.9gのものは成績が悪い赤玉土オンリーの状態なので、籾殻でやっていれば50%を超えた可能性があるかもしれません

表だと6gは重い方だけど、実際の挿し木は2〜3節でやる場合が多いから「軽すぎて失敗する」って事態はよっぽどじゃないと起こらなそうだね
まとめ:反省と改善点
今回は特に工夫もせずに容器と用土を用意し、特に加工をしていない挿し穂を使いましたので、それぞれの結果から得られた改善点をまとめていきます。
- 容器について
セルトレイには小さい排水穴しかないので排水性が悪く、赤玉土が泥化しやすい。 - 植え方
ヒーターマットで加温しているので、その恩恵を最大限受けるために深めに植えてしまった。その結果として葉が埋もれたり、湿度過多になったりしてしまった。 - 用土について
赤玉土は中粒だったので下の方の粒が潰れやすかった。籾殻は虫の発生源になったことと稲の発芽や謎のキノコの発生と別の生物を飼育する環境になりがちだった。 - 穂木について
今回は何も加工していなかったため、髄が食害を受けてしまった。
- 容器について
セルトレイに切れ込みを入れて排水能力を向上させるか、底面にキッチンペーパーなどを敷いて吸水させることで強制的に排水させる構造を用意すれば良かった。 - 植え方
乾燥しやすくなるので灌水の頻度を上げる必要があるかもしれないが、もっと浅植えにするか、葉や芽が押し除けやすい小粒の赤玉土にすれば良かった。 - 用土について
赤玉土は小粒にすることで、重量と荷重が分散するので潰れにくくなる可能性がある。籾殻に関しては面倒だが熱湯処理か黒ビニールで覆って日光に晒すことで高温処理をすればキノコや稲が生えにくくて良かったかもしれない。 - 穂木について
食害対策に切断面にトップジンMペーストを塗るか、パラフィルムなどで覆えば直接髄が露出しないので良かったかもしれない。
機会があれば改善点に出てきたトップジンMペーストとパラフィルムコーティングのどちらが成績が良いのも試してみたい…。
ちなみにトップジンMペースト200gは普通に鉢栽培している分には使いきれない量ですが、挿し木の断面に塗るとなると、挿し穂1本あたりの消費量は大したことなくてもかなりの量を消費していますので、予定がある方は大きめのがあると良いかもしれません。


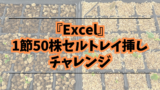
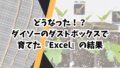

コメント